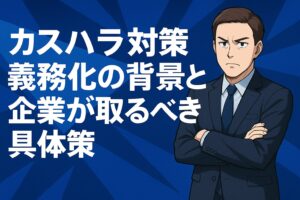【特集】厚労省、「労働者」の定義見直しへ ―40年ぶりの議論開始
最新ニュース法改正2025年5月11日
働き方の多様化と“保護されない労働者”の拡大に、制度は追いつけるのか?
厚生労働省は2025年5月、有識者による検討会を立ち上げ、法律上の「労働者」の定義の見直しに向けた議論を開始しました。これは、労働基準法が保護する「労働者」の範囲について、約40年ぶりに本格的な見直しに踏み切るものであり、フリーランスや業務委託契約といった“雇用関係にない就労形態”の急増を背景としています。
「労働者」の定義は、誰を守れていないのか?
現在、労働基準法第9条では「労働者」を「使用される者」と定義していますが、これはあくまで“雇用契約”に基づく就労者が対象です。
しかし実際には、
・指揮命令に従って働きながら、雇用契約ではなく業務委託扱いとなっている人
・就業時間が固定され、実質的に社員と同様の業務をしているフリーランスなど、「実態としては労働者だが、法律上は労働者と認められない」ケースが急増しています。
こうした働き手は、残業代・休憩・解雇ルールといった保護が及ばず、最低限の労働権さえも担保されない“グレーゾーン”に置かれているのが現実です。
組合の立場から見ると?
私たちマルエツエクスペリエンス労働組合(ME-UNION)にとっても、この動きは決して他人事ではありません。というのも、組合が向き合う現場には、非正規や深夜勤務など“見えにくい働き方”をしている従業員が多数存在しているからです。
・契約形態によって、同じ仕事でも処遇が異なる
・雇用関係が曖昧な人は、団体交渉や相談の場にすら届きづらい
こうした現場の課題に対して、法律上の定義が追いついていないことが、改善の障壁になってきたのです。
「保護されるべき労働者」は、制度が追いつかなくても存在している
今回の厚労省の動きは、「働き方が多様化したから仕方ない」で済まされていた現実に、ついに制度側がメスを入れようとしている、極めて大きな一歩です。しかし、制度が変わるまでには時間がかかります。だからこそ、私たち組合は現場の声を集め、「制度が変わる前から、守られる職場環境」を作る努力を続けなければなりません。
最後に:定義は“後からついてくる”、でも声は“今”から届く
誰が「労働者」なのか――その線引きを変えることは簡単ではありません。でも、「働く人の声が無視される社会を変える」第一歩は、いつでも現場から始められます。
マルエツエクスペリエンス労働組合は、これからもすべての働く人の立場に寄り添い、制度の谷間に取り残されないための「声」と「力」を届け続けていきます。
マルエツエクスペリエンス労働組合
運営事務局:me.union0703@gmail.com
相談フォーム:https://forms.gle/CG8bmJ4fpuBivK3f9
本記事は、各種報道および公表されている情報をもとに、労働組合の立場から整理・解説したものです。法律や制度の詳細な運用については、厚生労働省などの公的機関による正式な発表やガイドラインをご確認ください。